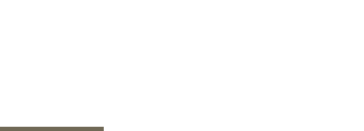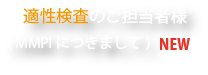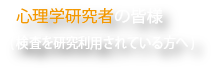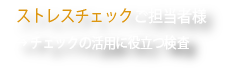うつ状態の方は暗く沈んで何をする意欲も起こらない気分です
うつ状態の方は暗く沈んで何をする意欲も起こらない気分です
うつ状態になると暗く沈んで何をする意欲も起きません。気分は憂鬱で、表情も沈み、寂しいと常に訴えます。さらに、考えや決断力が低下して、思考のテンポも遅くなったり思考できなくなったりします。動作も緩慢になり、いつもしていた簡単な仕事もできなくなります。さらに様々な妄想や幻覚が伴うこともあります。
 現代ではうつ病は非常にありふれた病気です
現代ではうつ病は非常にありふれた病気です
生活環境の変化、経済的な変化、またうつ病に対する認知度の向上により、うつ病と診断される患者は増えています。精神疾患の中でも不安障害についでよく見られます。一般診療科を受診する患者さんの約10人に1人がうつ病と言われることもあるほどです。初めから精神科を受診される患者よりも、体の症状に基づいて内科を受診される患者が圧倒的に多いです。
 うつ状態とうつ病は全く同じものではありません
うつ状態とうつ病は全く同じものではありません
うつ状態は精神医療において最も頻繁に見られる状態で、うつ病以外にも様々な原因によって引き起こされる可能性があります。DSMでは、1日の大半、またはほぼ毎日、2~3週間はうつ状態であり、さらに著しい機能的な障害を引き起こすほど重症である場合を大うつ病エピソードとして定義しています。
 うつ病による自殺は軽快期に起きることも多いです
うつ病による自殺は軽快期に起きることも多いです
自殺を考えるのはうつ病の人にみられる最も深刻な症状です。多くの患者は「死にたい」あるいは「自分には価値がないから死ぬべきだ」と考えていて、治療を受けていない人が自殺に至るリスクはかなり高いと言えます。また治療を受けていてうつ病が治りかけている時期(軽快期)に自殺するケースもあります。うつ病が重度の時は自殺する気力も体力もないという場合があるからです。
 うつ病と不安障害は併発することがよくあります
うつ病と不安障害は併発することがよくあります
DSMには不安と抑うつの併存(comorbidity)という考え方が導入されています。実際に、多くの不安障害を持つ患者にうつ病の併発が認められ、また逆にうつ病の患者に不安障害が併発するケースもよくあります。うつ病を有する方のうち50%以上が不安障害を併発していたというデータも得られています。うつ病は、単一の疾患ではなく症候群として捕らえることが必要と考えられます。
 うつ病は遺伝的背景・性格的背景・状況が重なり発症するようです
うつ病は遺伝的背景・性格的背景・状況が重なり発症するようです
気分障害の項で説明したように、うつ病の要因にも様々な仮説があり、はっきりと解明されてはいません。遺伝的背景(素因)・性格的背景(病前性格)、そして発病につながるような身の回りの状況、これらの複合的な作用により発症に至ると考えられています。同じようなストレスを受ける環境にあっても、全員がうつ病になるわけではありません(ストレス脆弱性モデルに基づく)。
 遺伝的素因はうつ病の発症に関与していることは明らかです
遺伝的素因はうつ病の発症に関与していることは明らかです
血縁のある親族にうつ病の人がいる人はいない人に比べて1.5~3倍発症しやすいことから、うつ病の発症に遺伝的要因が関与していることは明らかです。具体的にはセロトニントランスポーター遺伝子がうつ病に関与していることは知られていますし、さらにどの遺伝子がうつ病に関与しているのかプロテオミクスなどによる網羅的解析が行われています。
 メランコリー親和型などうつ病になりやすい性格が存在します
メランコリー親和型などうつ病になりやすい性格が存在します
几帳面な方、完璧主義者、真正直な方、あるいは自分の中に閉じこもることが多い方、こういった方はうつ病になりやすい性格の方と言えます。代表的なうつ病になりやすい性格傾向にメランコリー親和型性格があります。人に気をつかいすぎてストレスを溜め込みやすい性格なので、適度に適当に振る舞い、ストレスを発散する方法を持つことが大切です。自分の性格を理解し、早めに精神科・心療内科を受診した方がよいです。
 様々な身近にある変化がうつ病発症のきっかけになります
様々な身近にある変化がうつ病発症のきっかけになります
誰でも体験しうる身近な状況の変化がうつ病発症のきっかけになることがあります。特によく見られるのが以下の4つのケースです。①病気やけがなどに対する不安がある場合
②子供の独立や失業・退職など人間関係や地位に変化があった場合
③親しい人と死別、離別した場合
④結婚、出産、転校、就職など環境が変化した場合
特に4番目はどちらかと言えば喜ばしい変化ですが、これがうつ病に結びつくこともあります。いずれにせよ、要因がはっきりしている場合は、うつ病が治りやすいと言われているので、要因を精査することは重要です。