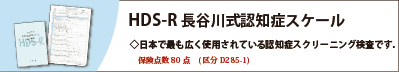認知機能の評価は認知症の中核症状の評価であり大切です
認知機能の評価は認知症の中核症状の評価であり大切です
患者さんの様子を十分観察し、患者本人と付き添いの人からの病歴を聴取できたら、次は認知機能の評価に移ります。認知機能障害は認知症の中核症状であるため慎重な評価が必要です。また、認知症の原因疾患によって障害のパターンが異なるので、できるだけ詳細な評価が求められます。記憶、見当識、言語、遂行機能、視覚認知、構成、注意などの認知症によって傷害されやすい認知機能について、それぞれの機能障害の有無を検討できればベストと言えます。
 いきなり検査を行わず、まず問診の中で認知機能を確認できます
いきなり検査を行わず、まず問診の中で認知機能を確認できます
長谷川式認知症スケール(HDS-R)などの認知症検査は簡便なスクリーニング検査ですが、いきなり検査を実施するとなるとどうしても患者さんは身構えてしまいます。そこで最初は簡単な質問をして緊張を和らげながら、同時に認知機能を確認するのが有用です。「生年月日はいつですか」「昨日の夜は何を食べましたか」といった日常的な質問であれば、抵抗なく答えることができます。自然な会話の中の質問により、まず簡単に患者さんの認知機能を把握します。
 認知症のスクリーニング検査として長谷川式認知症スケールが広く用いられています
認知症のスクリーニング検査として長谷川式認知症スケールが広く用いられています
さらに詳細に認知機能を診察するために、認知症のスクリーニング検査が用いられています。いくつかの種類がありますが、臨床現場では
長谷川式認知症スケール(HDS-R)が最も広く用いられています。スクリーニング検査としてだけでなく、どの項目でどのように間違えたかを見ることで、認知機能の障害パターンを知ることも可能です。一見シンプルな検査ですが、患者さんの様子・態度を詳しく観察することで、得点以外の様々なデータが得られます。詳しくは
長谷川式認知症スケールのページをご覧ください。
 補助診断として画像検査の活用も有用です
補助診断として画像検査の活用も有用です
MRI、CT、SPECTなどの画像検査の精度も上がってきており、幅広く用いられています。MRI、CTでは脳血管障害や脳腫瘍の有無、脳萎縮の状態が確認できます。SPECTでは脳がどれだけ活動しているかを知ることができ、機能低下のパターンから鑑別診断にも役立ちます。一部の認知症は画像診断によってのみ診断が可能であり、認知症診断の際にはかかせないツールとなってきています。しかし、これらの画像検査はあくまでも診断の補助であり、問診や他の検査と組み合わせて総合的な診断を行うことが重要です。
 認知機能を把握した後は鑑別診断を行います
認知機能を把握した後は鑑別診断を行います
認知機能の低下が把握できたので、そこで認知症と診断することはできません。まずは、他の病気が原因で認知機能が低下していないか、他の病気との鑑別を行います。正常な老化でも認知機能は低下しますし、老年期うつ病やせん妄の患者には認知症と似た特徴が見られるので、これらとの鑑別が重要です。また、認知症であると確定した後は、認知症の原因疾患の鑑別を行います。これについては次項で取り上げます。このように、認知症と最終的な診断を行うには、さらなる検討が必要になってきます。