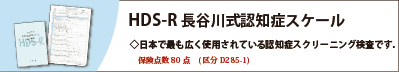認知症の症状は中核症状と周辺症状に分けられます
認知症の症状は中核症状と周辺症状に分けられます
認知症は脳の機能が低下することにより、多種多様な症状を示しますが、大きく中核症状と周辺症状に分けられます。
中核症状は患者全員に見られる症状であり、病気の進行とともに症状も徐々に進行します。記憶障害・見当識障害・認知機能障害などが含まれます。
周辺症状は患者によって出たり出なかったりする症状で、近年は
BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)、認知症の行動・心理症状と呼ばれています。興奮、暴力行為、妄想、うつ状態など様々な症状が含まれます。
 中核症状1:記憶障害
中核症状1:記憶障害
記憶障害は、自分が体験した出来事や過去に関する記憶が抜け落ちてしまうという障害です。老化によるもの忘れと異なり、もの忘れをしているという自覚がなく、日常生活に支障が出ます。最初は同じ事を繰り返す聞くようになったり、しまった場所を忘れて探し物が多くなったりします。そのうちに物をしまったことや、ご飯を食べたこと自体を忘れるようになり、さらに症状が進むと昔のことまで忘れてしまいます。
 中核症状2:抽象能力・判断力の低下
中核症状2:抽象能力・判断力の低下
認知症により抽象能力や判断力の低下が起きます。犬も猫も動物ですが、抽象能力が低下すると、具体的な「犬」「猫」はわかっても、2つを内包する「動物」という概念がわからなくなってしまいます。また判断力が低下すると、物事が良いか悪いかの判断ができなくなります。また、ジュースを冷蔵庫で冷やすのはいいのですが、判断力が低下すると、同時に買ってきた洗剤も冷蔵庫に入れてしまうようになります。物が捨てられなくなり、部屋がゴミだらけになることもあります。
 中核症状3:見当識障害
中核症状3:見当識障害
認知症の初期症状として記憶障害とともによく見られるのが、失行・失認などの見当識障害です。見当識とは、日付や時刻、自分が今どこにいるかなど基本的な状況把握のことを指し、これが正確に認識出来なくなるのが見当識障害です。初期段階では日付や時間を間違える事が多くなります。特に今何月かを間違えることは正常な人ではまずあり得ません。さらに今どこにいるかがわからなくなり、自宅さえもわからなくなってしまいます。また、人を認識することもできなくなります。