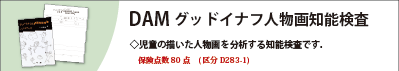子どもの心と大人の心には大きな違いがあります
子どもの心と大人の心には大きな違いがあります
内科と小児科が分かれているように、子どもの心と大人の心も分けて考えるべき全く異なる部分が多いです。ここでいう"子ども"は乳幼児期から学童期までを指しています。この期間は、人格構造が未熟、未分化であるため、症状が言語ではなく行動、精神症状よりも身体症状となって現れることが多いです。また、どんどん成長が進むために、症状も変化していきます。さらにこの時期は、大人に比べて親との関わり合い、友人との関わり合いが非常に重要になります。
 親子の関係は子どもの心身両面の成長の上で非常に重要です
親子の関係は子どもの心身両面の成長の上で非常に重要です
子どもにとって最も身近な存在は親であり、親から大きな影響を受けています。保護者の子どもに対する不適切な接し方が改善されることによって、子どもの精神障害が改善される例も多く見られています。子どもにとって拒否的な態度、冷淡な態度を取ってはいけませんし、反対に過保護になったり、過度に期待してもいけません。子育ては難しいと言いますが、うまくバランスの取れた接し方ができれば、子どもの心身共に健全な成長に結びつきます。
 児童期の精神障害1:自閉症
児童期の精神障害1:自閉症
自閉症はコミュニケーション障害や、極度の固執性、言語発達の遅れなどが主な症状の神経発生的な障害です。多くの場合、知的障害を伴います。先天性の脳機能障害と考えられていますが、その詳細なメカニズムは未だわかっていません。1~2歳といった乳幼児期から発病することも多く、遅くとも3歳までには発病します。様々な症状が見られ、その固執性から計算力や記憶力が優れているケースも見られます。
 児童期の精神障害2:注意欠陥・多動性障害(ADHD)
児童期の精神障害2:注意欠陥・多動性障害(ADHD)
注意欠陥・多動性障害(ADHD)は、新生児期までに何らかの脳器質的病変が起きたことによる障害です。その症状は、落ち着きのなさ、運動過多、注意力や集中力の欠如などの行動障害の形で現れます。この行動障害が原因で、授業についていけないなどの学習障害が見られることが多いです。発症率は5%前後で、近年AD/HDに対する認識が進むと共に患者数も増加傾向にあります。
 児童の精神障害3:精神遅滞
児童の精神障害3:精神遅滞
精神遅滞は知的障害とも呼ばれ、精神発達の途中で何らかの原因で知的機能を含む精神機能の発達が全体的に遅れる障害です。先天性の異常の場合もあれば、乳幼児期以降の障害が原因の場合も含めて、様々な事例が含まれます。知的機能の低下は、知的検査によって調べられます。近年、知的検査の使用自体が差別的だと批判されることがありますが、適切な知的検査の使用は患者さんの病状の正確な把握に繋がり、むしろ差別をなくす効果があり重要です。
 児童の精神障害4:不登校
児童の精神障害4:不登校
身体的・精神的にはっきりした症状が見られないのに登校しないのが不登校です。「登校したくない」場合だけでなく、「登校したいのにできない」という場合も含めて不登校と考えられています。学校そのものや、学校での人間関係に対する嫌悪や恐怖を、不登校という形で回避しようとしている点がほとんどで、精神障害として考えられています。カウンセラーや医師も含め、両親や教師と共に取り組んでいくべき重要な問題です。